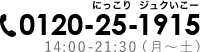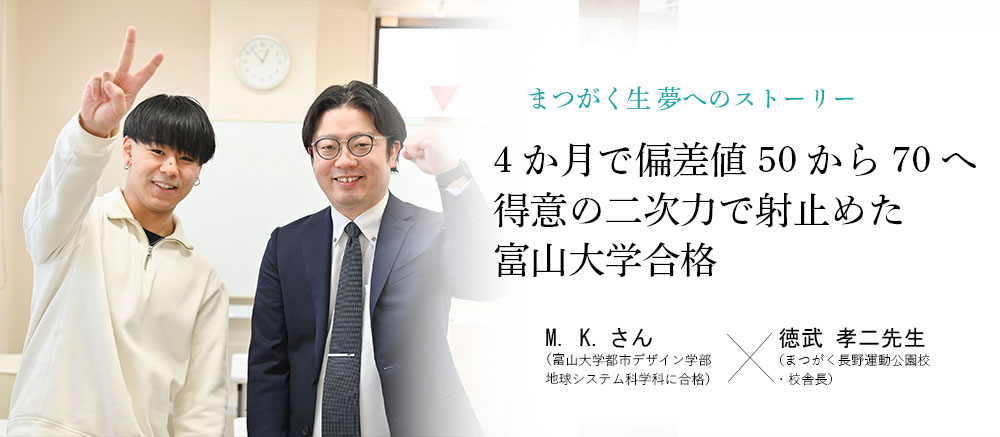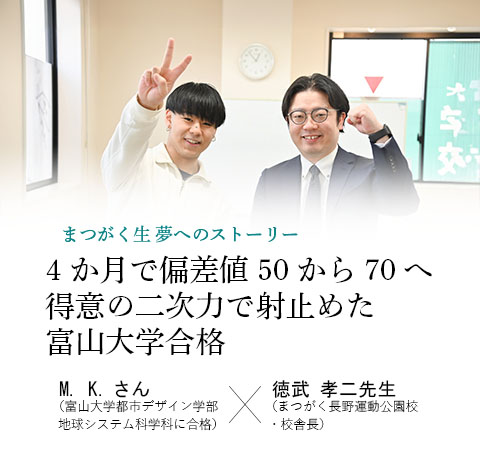長野日本大学高等学校2年生だったM. K.さんは、友人の言葉に発奮してまつがく長野運動公園校の扉をたたきました。毎日通塾し、短期間で大幅な伸びを記録するレアケースを現実のものにします。
もう一点宮澤さんがレアだったのは、共通テストのようなマーク式問題よりも、記述式問題が得意だったこと。このことで国公立を目指す受験期は苦しい思いもしましたが、最後大いに助けられました。
周囲の誰もが驚く変貌ぶりが呼び込んだ合格への道のりを、校舎長の徳武孝二先生と回想します。
M. K.さんのデータ
●出身校/長野日本大学高等学校 ●将来の夢/地震や地球科学の研究職
高2・9月 |
まつがく長野運動公園校に入塾。ほぼ毎日通塾していた。毎月1回、鶴吉雄一郎先生(現・まつがく長野駅東口校校舎長)が担当してお母様と懇談 |
|---|---|
高3・5月~12月 |
駿台atama+共通テスト模試や共通テストAI特訓で得点率が伸び悩む |
1月 |
共通テストではギリギリ国公立で戦える点数は確保。富山大学への出願を決める |
2月 |
・併願として日本大学、東京都市大学、芝浦工業大学、立命館大学を受験(4校とも合格) |
3月 |
富山大学に合格 |
1. 毎日通って数学の偏差値が50から70へ
ここしかない!

- 徳武
M. K.くんは高2の秋、9月に入塾しました。入塾に至るまで、実はかなり迷っていたと聞きました。
- M. K.
当時の俺は一般受験で戦える学力がなかったので、指定校推薦を考えたほうがいいんじゃないかと思っていました。だとしたら、塾でゴリゴリ勉強するよりは、学校の課題や探求学習をがんばったほうがいい。高2の6月に一度体験入塾してみて、そこからいろいろ考えた末に入塾しました。
- 徳武
入塾前の成績は、学年の中でどれくらいだったか覚えていますか?
- M. K.
高2の時は、270人中200位に届くか届かないかでした。将来のことも、当時は何となく地学系というイメージはぼんやりあったんですけど、まだまとまっていなかったです。
- 徳武
そういえば、将来の夢が「地震や地球科学の研究職」ということで、小学生の時から地震災害に関心があったそうですね。
- M. K.
印象に残っているのは熊本の地震ですね。東日本大震災は幼稚園の時でした。地震がなぜ起きるのかというメカニズムに興味があります。
- 徳武
なるほど。そして入塾は「絶対国公立へ連れて行くからうちに来い!」という熱い言葉が決め手になったそうなんですが、この言葉は当初窓口だった前・校舎長の鶴吉先生ですね。
- M. K.
もうここしかねぇな、みたいな感じでした(笑)。それに、まつがくは自学を重視しているのが僕には合っていました。
絶対無理に決まってる

- 徳武
最初は、英語と数学の土台を固めるためにatama+をはじめてもらいました。AI学習ははじめてだった?
- M. K.
めちゃくちゃ新鮮だったし、自分に合っているなと感じました。
- 徳武
ほぼ毎日通塾して、平日は3、4時間、休日は8時間以上学習していて、長野運動公園校で1、2を争うほどでした。急にこんなにガラッと変わって、M. K.くんの中ではどういう変化があったんですか?
- M. K.
そんなに勉強していた記憶はなかったです。勉強ができなかった時に周りにイキり散らかして「俺、国立行きてぇわ」って言って、友だちに馬鹿にされたんです。それも塾に入ろうと思ったきっかけでした。「おめぇな、絶対無理に決まってんだろ」とかめちゃくちゃ言われていたので、見返してやるという気持ちが原動力になっていたのかもしれないです。
- 徳武
部活をやっていなかったから、放課後の時間をすべてまつがくに充てて。atama+以外もやっていたよね。
- M. K.
入塾する前からイキって『チャート式』をやってて、愛着があったので続けてました。
- 徳武
質問もよくしてくれていました。使う教材もそうだし、何をやったらいいかM. K.くんの中で迷いがある時に相談してくれました。「このタイミングでこれを、どれくらいやればいいですかね」と聞いてきたのを覚えていますよ。atama+も網羅的に全部一からやるというよりは、自分が今、身につけないといけない分野に絞って重点的にやってくれていました。数学はもともと得意だったんだよね。
- M. K.
そうですね。レベル的には、ちょっとできるぐらいです。
- 徳武
力がついてきたと感じ始めたのはどのタイミングですか。
- M. K.
4か月後ぐらいに受けた進研模試です。11月は偏差値が50ちょっとしかなかったのが、1月は70行くか行かないかくらいまで上がっていました。
- 徳武
これだけのジャンプアップは、稀に見る珍しいケースです。お母様も驚いていたよね。月1回の懇談で、鶴吉先生から「お母さんからありがたいお言葉をいただいた」と聞いていました。本当に毎日来ていたからね。高1の時は全然勉強してなかったというM. K.くんが180度変わって、親御さんとしても感じるところがあったんじゃないかと思います。
- M. K.
結構心配されていたんですけど、勉強していることはすごく褒めてくれていました。
- 徳武
理科・社会・国語についてはどうでしたか?
- M. K.
理科は物理だけatama+で取っていました。数学が比較的得意だったこともあって、数学に偏りがちで。高3の初めぐらいまでは、数学以外何もできない状態でした。
- 徳武
確かに、英語はあまり触れていない印象だったね。
- M. K.
単語帳だけやっていました。高3になってから、理科・社会・国語については共通テストの対策本をやっていました。社会は現代社会です。
2. マーク式問題に長く苦戦
二次試験で勝負しよう
- 徳武
高3に入ってから、「駿台atama+AI特訓」をはじめました。これは共通テスト対策のための特別プログラムで、駿台予備校とatama+をドッキングさせて、共通テスト向けの模試とその結果の分析とそのためにやるべき単元などを提案するというものです。ここで得点率が伸び悩むようになりました。
- M. K.
全然ダメでした。
- 徳武
マーク式のテストが苦手だったよね。M. K.くんの場合、回答の筋道を固定されてしまうと力を発揮するのが難しくなって、逆に記述式のほうが安定していました。記述力に苦手意識を持つ学生さんのほうが圧倒的に多いので、珍しいタイプだったと思います。
- M. K.
マーク式が苦手だったのはもうひとつ理由があって、制限時間の厳しさです。もともと緊張するタイプだったこともあって、ストレスになっていました。
- 徳武
共通テストは時間がタイトだもんね。じっくり考える時間はなくて、さっさと解いていかないと間に合わない。二次試験のほうが問題数は少なくて時間に余裕があります。
- M. K.
3年に入ってから12月まで、共通テスト対策については結構長いこと伸び悩んでいました。
- 徳武
AI特訓は5回あって、その中でなかなかM. K.くんの満足する結果が出せなくて、志望校の合格ラインに届くまで苦労していました。スランプというよりは、こういうタイプの問題で自分のパフォーマンスをうまく出すのが苦手なんだと思います。もうひとりのスタッフとも、どういうアドバイスをしようかとよく話し合っていました。一方で、記述力、つまり二次力が強いこともはっきりしていたので、共通テストのボーダーラインにはできるだけ近づけつつ、二次で勝負する戦略がM. K.くんにはベストなんじゃないかと考えていました。そういえば、富山大という話はどの段階で出てきたんですか?
- M. K.
第一志望は、実は埼玉大学だったんです。埼玉大は二次の配点が低くて共通テスト重視なので、自分には無理だなと思ったのが3年の夏休み明け。そこから富山大が浮上してきました。ただ、よくよく見てみると、富山大は共通テストの配点が約63%で二次が37%。埼玉大は二次が30%だったので、7%しか違わなかったんですよね。行きたい学部で考えると、偏差値もそんなに変わらなかった。この点については、自分的にはやらかしてしまったなと……。
ギリギリ耐えて国公立で戦えるラインに

- 徳武
共通テストは大事だけどボーダーをクリアできるところまでがんばって、必要以上にフォーカスしすぎないようにする。そして得意の二次を磨いていく戦略になりました。それでも、モチベーションの維持はなかなかつらかったんじゃないかと思いますが。
- M. K.
12月はマジで死にかけていました。1月に入って二次で行くしかないとなった直後に、精神的に吹っ切れました。
- 徳武
直前期は勉強のペースもさらに上がっていて、休日は朝から晩までやっていました。共通テストが終わった後は、そんなに心がブレることもなく、「二次一本でいきます」と言っていて、そのあたりは気持ちのコントロールがよくできていたよね。
- M. K.
自分としては、学習量はあんまり変わっていない感覚でした。
- 徳武
共通テスト前日も塾に来てくれて。
- M. K.
社会の確認を少しするくらいで、もう勉強はあんまりしていなかったです。
- 徳武
共通テスト本番の手ごたえはどうでしたか?
- M. K.
数学ⅡBはめちゃくちゃ良かったんですけど、数学ⅠAが本当に壊滅的だったので、人生終わったなって感じでした。学校でとなりの席の子たちが得点できていたみたいなので、余計にもう終わったな……って。
- 徳武
数学ⅠAが壊滅的になったのは、自分ではどう分析していますか?
- M. K.
問題自体はそんなに難しくなかった印象なんですが、最初のちょっとしたところで計算ミスして、それで崩れてしまった感じです。
- 徳武
共通テストの難しいところですね。とはいえ、ギリギリ国公立で戦えるだけの得点はできました。
- M. K.
一応耐えたな、ぐらいは(笑)。
- 徳武
共通テスト後にまつがくに来た時は、気持ちが切り替わっていましたね。割り切って必要以上に落ち込まずという感じで。
- M. K.
ただ、「共通テストリサーチ」では富山大はE判定だったんですよね。
- 徳武
共通テストリサーチというのは、共通テスト受験生の自己採点結果・志望校を集計してボーダーラインの予測を行うサービスで、河合塾が提供しています。二次試験をどうするか、考える指標になります。本当によく踏ん張ってくれたと思いますよ。勝負できる国公立はあるので、得意の二次力で何とか行けるかなと。それでここから、過去問を10年分やってもらいました。
- M. K.
共通テスト前までは共通テスト対策に全振りしていたので、二次対策はここから本番でした。
蓋を開けてみたら……
- M. K.
同時に併願の私大対策もはじめました。英語は捨てていたので、数学と物理に集中していました。
- 徳武
私立は日本大学、東京都市大学、芝浦工業大学、そしてこっそり立命館大学にも出願していたとか。
- M. K.
申し込みの日が国立前期の日だったので、親に「出さなくていいよ」と伝えたんですけど、「もう出しちゃった」と言っていて。落ちるだろうと思っていたので、誰にも言わなかったんです。
- 徳武
試験日の順番は?
- M. K.
日大、東京都市大、芝浦工大と続いて、国立前期試験。その後に立命館でした。
- 徳武
私立の手応えはどうでしたか。
- M. K.
日大と都市大がダメで、芝浦工大と立命館が良かったです。
- 徳武
蓋を開けてみたら全部合格していましたね。
- M. K.
日大は、附属高校生は受験料が無料になるんです。それで、いろんな学部に出願しまくったのが功を奏したんじゃないかと思います。
- 徳武
富山大の前期試験はどうでしたか。
- M. K.
周りは「めちゃくちゃ難しかった」と言っていたんですが、俺はかなり手ごたえがありました。だから、その後の立命館は「もういいかな」と流す感じでした。
- 徳武
芝浦工大に行きたい気持ちもあったんだよね。
- M. K.
目指していた時期があったので、合格したら迷いましたね。ただ学費が高くて、俺が合格した学科は確か200万円を超えていたと思います。母は「お前の人生だから好きに決めなさい。私立でもいいよ」と言ってくれていたんですけど、学費があまりに違う。親にあまり負担をかけたくなかったので。俺はどちらに行くとしても満足だったので、富山大に決めました。
3. 得意を活かして狙って勝負する
厳しいと言い続けた先生が泣いた
- 徳武
共通テストが会心の出来というわけではなくて、二次でどこまで挽回できたかがカギだったので、フィフティ・フィフティかなと思っていました。だから、合格の報せを聞いてほっとしましたよ。前に「お前には絶対無理」と言っていた友だちは?
- M. K.
そういうことを言ってきたヤツのほうが喜んでくれました。
- 徳武
学校の先生は、泣いてくれたとか。
- M. K.
担任とお世話になった数学の先生が、少し泣いていました。多分、俺が受かるとは思ってなかったんだと思います。
- 徳武
まつがくに通うようになって、勉強に対する姿勢も学力も変わりました。そのあたりは、学校の先生はどう見ていたんだろう。
- M. K.
国公立を目指すとなると、共通テストも二次もどちらも必要です。でも俺は、二次は伸びても共通テストが全然伸びなかったんで、担任の先生からは「こんなに差がある人はいない。前例がない。合格は厳しいかもしれない」と心配されていたんです。無理とは言わないけど、それに近い感じのことをずっと言われていました。だから、俺が一般入試を受けることにもあんまり賛成ではなかったです。
- 徳武
総合型選抜や指定校の話はあったのかな。
- M. K.
授業態度が悪すぎて評定はゴミレベルで、一般入試しかねぇ、って感じでした。
大学受験を通して得た力と気づき
- 徳武
まつがくに入って変わったこととして、「理系的思考を要するものへの対応力が変わった」と書いてくれています。
- M. K.
大学入試はある程度パターン化されたものを自分で使いこなすことも大事で、それを理系的思考と呼んでいいか分からないですけど、パターン化されたことをしっかり自分の中に吸収して、それを運用する力がついたと思います。
- 徳武
そこは我々もとても大事にしているところです。応用問題も結局は基礎の組み合わせで解いていくので、基礎をしっかり固めて応用できる力を身につけてほしいんですよね。その力が身についたと言ってもらえるのは、すごく嬉しいです。
- M. K.
その対応力を日常生活でも応用できるようになったと感じています。共通テストが終わって、ドラムを再開したんですよね。ドラムも基礎が大事だなと思って基本的な練習を繰り返したら、まだ1,2か月しか経っていないですけど、上達している実感があります。
- 徳武
すごいなぁ。学習だけじゃなく、他のことにも応用できているのは素晴らしい! 大学に入ってから楽しみにしていることはある?
- M. K.
軽音はやりたいですね。あとは友だちをいっぱいつくりたい。コミュニケーション力を上げたいです。
- 徳武
M. K.くんは友だち多いよね。まつがくでも、同級生と休み時間に談笑しながらご飯食べていたり。仲間と切磋琢磨していたのも、合格までがんばれた要因かなと思います。
- 徳武
これから受験する人に、アドバイスやメッセージはありますか?
- M. K.
ふたつあって、まずひとつ目は「得意科目を活かしきる」です。さっきも言ったように、国公立は共通テストの配点が高い場合が多いので、まんべんなくできないといけないのがセオリーです。ただ逆に、配点の低い二次でも最大限の力を出しきれれば受かる可能性はあります。実際、自分の共通テスト後の判定はEでした。そんな絶望的な状況でも、二次試験が取れたので受かりました。二次試験が自分の得意科目で勝負できるんだったら、突っ込んでも全然いいんじゃないかと思います。
- 徳武
説得力があるね。あともうひとつはなんでしょうか。
- M. K.
「自分が勝負しやすいところをちゃんと狙っていく」です。富山大は二次が物理と数学だけで、立命館もそうなんです。自分の得意を活かせるところを狙って受験しました。探してみると、いろんな形式があるんですよね。
- 徳武
M. K.くんは、そういう戦略的な面でもがんばりましたよね。
- M. K.
受験期は周りのほうがすごくできるように見えるから、自分の得意科目といえども不安になるんですよね。でも、自分が明らかに得意だと思っている科目はだいたい周りよりも突き抜けていると分かりました。得意だと思っているなら、それを貫いてほしいですね。
- 徳武
M. K.くんが言ってくれた通り、全科目をバランスよくやる、苦手を克服していくのはスタンダードな考え方です。M. K.くんには自分の得意なもので突き抜けたほうが合うというのは僕も感じていたので、途中からは「(苦手科目を)もっとやれ」というような発言はなるべくしないようして、考えを尊重していました。話してくれる戦略も論理的で、目標によっては、苦手科目も足を引っ張らない程度にできていればOKというのは全然ありだと思います。
- M. K.
共通テストは苦手な人はずっと苦手なままだと思うんですよ。自分は結構やりましたけど、伸びなかったので。人を選ぶテストなのかもしれないです。目標が中堅クラスならば、二次を全開でぶっ飛ばしていけば戦えると思います。
- 徳武
その点で言うと、個別最適化された学習やプランがより大事だなというのは、改めて感じました。M. K.くんは今年の受験生を代表するくらい勉強をがんばっていたので、大学でも同じようにがんばってほしいですね。
(取材・文/くりもときょうこ)